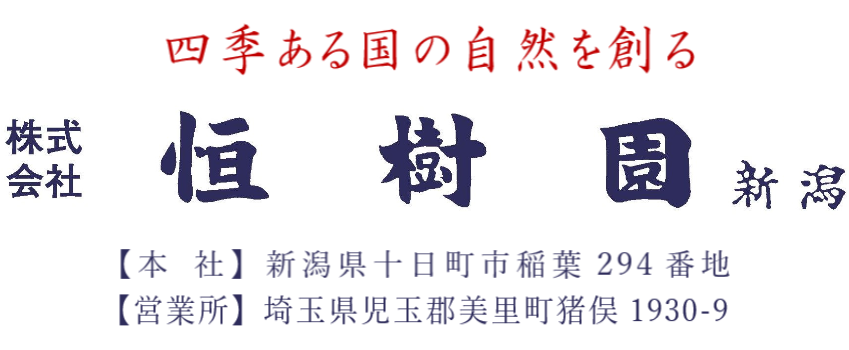今月の草木花
【冬の七草】
冬の七草は、春の七草や秋の七草のような古事に基づくものは見られませんが、明治37年の元日の
「時事新報」に伊藤篤太郎氏の考説として選定したものが掲載されました。
この時の冬の七草を今回は取り上げてみます。

【款冬の薹】フキノトウ
古くはフブキ(布々岐)などと呼ばれフブキが
つまって蕗になったといわれます。
食用のほか民間薬にも利用されます。

【福寿草】フクジュソウ
新年を祝うめでたい花として付けられた名前が
福寿草。ほかに元日草、賀正蘭の別名もあり、
江戸時代から盛んに栽培されてきた山草です。

【節分草】セツブンソウ
関東以西に分布し、花期は2~3月。旧暦の節分
のころに咲くので節分草といわれます。
可愛らしい山草として好まれているせいか、秩
父の周辺でも保護されているところ以外ではほ
とんど見かけられなくなっています。

【雪割草】ユキワリソウ
ユキワリソウと呼ばれるいるほとんどがスハマ
ソウかミスミソウです。早春に花を開くことと
個体変化に富んでいるため、江戸時代から盛ん
に栽培されてきた山草です。

【寒葵】カンアオイ
常緑性で冬も枯れずに花が開くので、寒葵の名前
がつけられました。斑入りのものもあるところか
ら古典園芸植物として栽培されています。

【寒菊】カンギク
寒菊にはいろいろありますが、とりわけ黄色の
ものが多くあります。9月頃枝を挿して根を付け
させ鉢に移すと、12月頃から花をつけ始めます。
花の少なくなってきた頃に咲くため重宝されて
きました。

【水仙】スイセン
日本の野生の水仙は、春のさきがけというには
早すぎる、凍える頃に咲いています。
中国、ヨーロッパから入ってきたスイセンなど
多種な花を咲かせ春を彩ってくれます。